最近では、難聴は認知症のリスクの1つだと注目されました。
加齢性難聴は多くの人が高齢になってから発症すると考えていますが、実際には20 代から始まることもあるとされています。
一般的には、50 代になると小さい音や高い音が聞こえにくくなり、さらに進行すると60 代後半では男女ともに半数近くが加齢性難聴を経験するという調査結果もあります。
| ■加齢性難聴は少しずつ進行し、気がつきにくい |
加齢性難聴は感音難聴に分類され、音の伝わる経路全体の働きが悪くなることで起こります。
音を感じるセンサーである有毛細胞は、中耳にある蝸牛(カタツムリのような形をした構造)の中に存在し、これらの有毛細胞が年齢を重ねるにつれて折れたり曲がったりすることが、加齢性難聴の主な原因の一つとされています。
有毛細胞は高い音を感じる順に蝸牛の入り口から並んでいるため、加齢性難聴は高い音から聞き取りにくくなります。
英語で蚊のことを「モスキート(Mosquito)」と言いますが、ブーンと蚊が飛んでいるような高い音のことを「モスキート音」と呼びます。
成人のほとんどは、18,000 Hz のモスキート音を聞くことができないといわれています。
以下のような症状が出ると、加齢性難聴の可能性があります。
◆ テレビのボリュームを以前よりも上げるようになり、家族からうるさいと言われる
◆ ピピッという電子音、携帯電話の着信音が聞こえない
◆ 女性や子どもの声が聞き取りにくい
◆ 「さ行」「か行」「は行」の聞き分けが難しい
| ■うつや認知症の原因になることも |
加齢性難聴は、うつや認知症の原因にもなることが分かっています。
加齢性難聴によりコミュニケーションが減少すると、会話を通じて脳に入ってくる情報が少なくなり、それが脳の機能の低下につながると考えられます。
その結果、うつや認知症のリスクを高める要因となります。
| ■補聴器を利用して、聴力の機能の回復を |
声や音が聞き取りにくくなったら、耳鼻咽喉科で加齢性難聴かどうか診断を受けることが大切です。
加齢性難聴は治すことはできませんが、補聴器を利用して聞こえを改善することができます。
難聴が軽度なうちに補聴器を使い始めることで、コミュニケーションに支障をきたすことなく生活ができ、うつや認知症の予防にもつながります。
日本では欧米と比較して補聴器に抵抗を感じる方も多いといわれていますが、聞こえを改善することがこれから先の健康、そして人生に大きな影響を与えます。
補聴器を適切に使用することで、社会的な孤立を防ぎ、積極的なコミュニケーションを維持することが可能となります。
| 認知症のリスク因子の中で、対策可能なことで最もその影響力が大きいのが難聴です。 もしも世界から難聴がなくなったとしたら、認知症患者を8%減少すると言われています。 難聴を予防することは、認知症を未然に防ぐことに直結するということです。 |
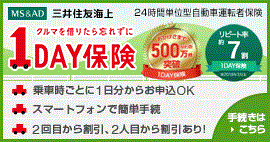 三井住友海上【公式】1日自動車保険はこちら↑
三井住友海上【公式】1日自動車保険はこちら↑
アドバンスリンクLINE公式アカウント
下記ボタンからアドバンスLINE公式アカウントと友だちになります
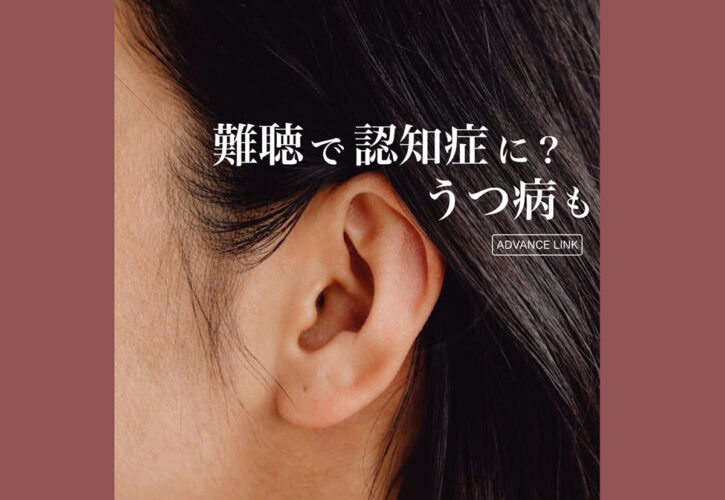
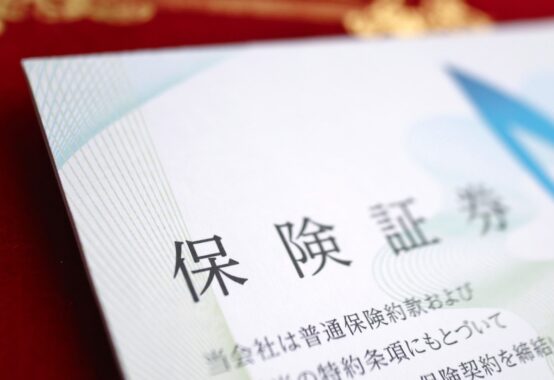







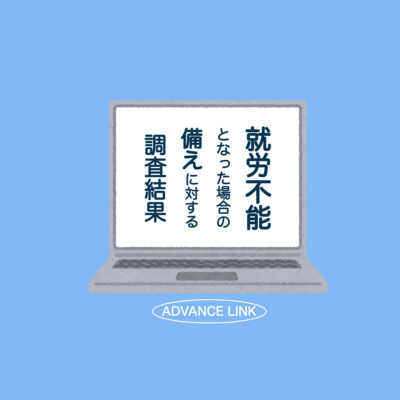
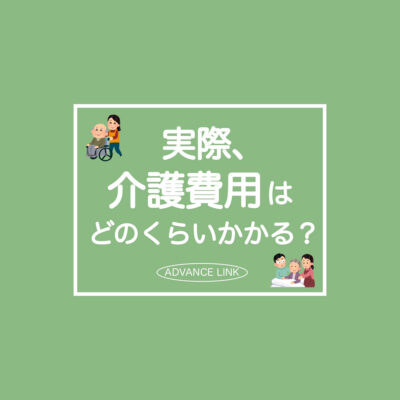
この記事へのコメントはありません。