1カ月(同じ月の 1 日~末日)の病院などでの窓口負担額が自己負担限度額を超えたときに、その超えた金額が公的医療保険から支給される 「高額療養費制度」について、勘違いしやすい事項をまとめました。
| ■ 対象となる自己負担額(すべての負担額が合算できるわけではありません。) |
対象になるのは公的医療保険適用の医療費で、受診者別 、医療機関別、医科・歯科別、入院・通院別で算出し、21,000円以上のものとなり合算されます 。
※内科や外科等は合算され、歯科のみが別の計算。
70歳以上の方は自己負担額全額が対象となります。
院外薬局で支払った薬代は処方元の医療費に合算します。
入院時の食事代、希望した差額ベッド代、先進医療にかかる費用、レーシックやインプラント等の保険適用外の医療費は高額療養費の対象外となります。
治療が月をまたいだ場合はそれぞれの月単位で自己負担額を計算するため、期間が1ヵ月で収まった場合に比べ、またいだ場合は医療費負担が高くなります 。

| ■ 世帯合算(世帯だからすべて合算できるわけではありません) |
同一世帯で、同じ月に、自己負担額が 21,000 円以上のものが2 回以上あった場合 、同じ公的医療保険制度に加入している場合は、家族の分も合算できます。
※同じ公的医療保険に加入している場合 とは、75歳未満の場合、健康保険証の記号番号が同一の場合75歳以上になると後期高齢者医療制度に加入するため、75 歳未満の家族とは合算できません。
合算できる自己負担額は上記 「 ■ 対象となる自己負担額 」 に同じです。
| ■ 多数回 (4回目の制度利用だからすべて適用になるわけではありません。) |
医療機関にかかって直近 12 ヶ月の間に同一世帯で3 回以上高額療養費が支給された場合、 4 回目以降 からは「多数回」に該当となり、自己負担限度額が軽減されます 。
ただし、退職や転職等により健康保険組合から国民健康保険に加入した場合など、 健康保険組合、全国健康保険協会(協会けんぽ)、市町村国保、国民健康保険組合、共済組合などの健康保険事業の運営主体である保険者が変わった場合には支給回数は通算されません。
| ■ 高額介護合算療養費(公的医療保険と公的介護保険を合算できる制度) |
世帯内に公的介護保険の受給者がいる場合、 1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)にかかった公的医療保険と公的介護保険の自己負担合計額が各所得区分に設定された限度額を超えた場合に、限度額を超えた額を支給する「高額介護合算療養費」という制度もあります。
| ■ 特定疾病療養費(高額な医療費が必要となる特定疾病の高額療養費制度) |
慢性腎不全・血友病等の治療を受けている方など著しく高額な医療費が必要となる特定疾病については、さらに自己負担の軽減を図る 「 特定疾病療養費 」 があります。
| 高額療養費の消滅時効は原則、診療を受けた月の翌月の初日から2年間で過ぎると支給を受けられなくなります。 限度額適用認定証やマイナンバーカードを健康保険証として利用すれば窓口で高額療養費制度が適用され清算されますので消滅時効の心配はありません。 |
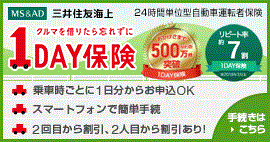 三井住友海上【公式】1日自動車保険はこちら↑
三井住友海上【公式】1日自動車保険はこちら↑
アドバンスリンクLINE公式アカウント
下記ボタンからアドバンスLINE公式アカウントと友だちになります

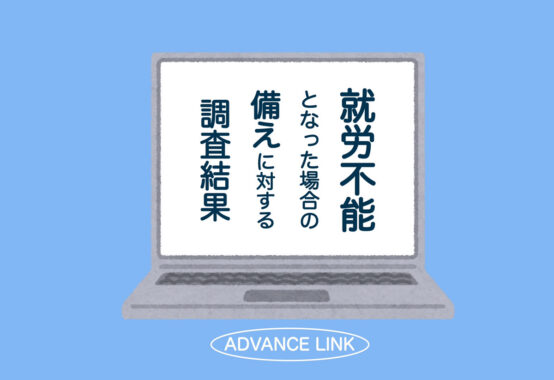



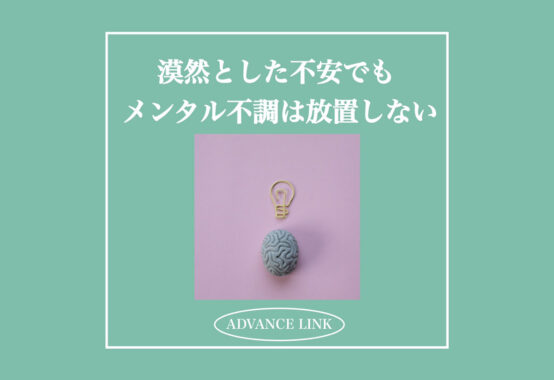
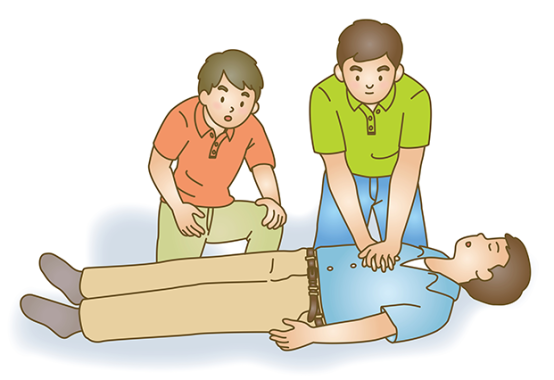



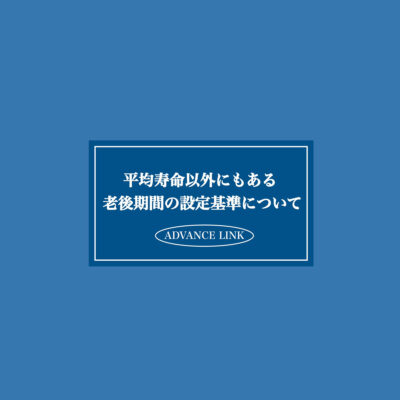
この記事へのコメントはありません。