日本が超高齢社会となった現在、加齢による判断能力の低下につけ込まれ、詐欺被害などに遭ってしまう事件が頻発しています。
財産を守る方法として注目されている成年後見制度について、利用増加の背景と制度概要を確認しましょう。
| 世帯高齢化で犯罪被害に遭う懸念も高まる |
国立社会保障・人口問題研究所の推計によると、世帯主が65歳以上の一般世帯が一般世帯総数に占める割合は、2020年の37.6%から2050年には 45.7%へ増加すると試算されています。
同様に65歳以上の単独世帯も13.2%から20.6%への増加が見込まれ、少子高齢化に歯止めがかからなければ世帯の高齢化も一層進むようです。
また厚生労働省の資料では、2022年における65歳以上の人に占める認知症有病率は12.3%、軽度認知障害の有病率は15.5%と報告されています。
近年は認知症の治療薬や予防プログラムの研究も進んでいますが、多くの人にとって発症後の完治は難しいと言えるでしょう。
高齢世帯の心配事として健康状態のほか、詐欺などの犯罪被害に遭いやすいことが挙げられます。
数千万円が騙し取られたというニュースも度々報じられており、何らかの方法で財産を守りたいと考える人は少なくないでしょう。
こうした状況もあってか最近注目されているのが、成年後見制度です。
| 市区町村長による生年後見人等の選任申立て件数が増加 |
成年後見制度とは、認知症や精神障害などによって物事を判断することが難しい人について、本人の権利を守る人(後見人等)を選ぶことで法律的に支援する制度です。後見人等を選ぶ方法は以下の2つです。
法定後見制度・・・本人の判断能力が不十分になった後に、家庭裁判所が個々の事案に応じて後見人等を選任
任意後見制度・・・本人が十分な判断能力を有する時に、あらかじめ任意後見人やその権限を自分で決めておく
法定後見制度では本人の判断能力に応じて「補助」「補佐」「後見」というタイプに分かれ、支援する人が代わりに行える財産管理、契約、協議などの権限の強さも異なります。
こちらの利用にあたっては本人や親族が家庭裁判所へ申立てを行いますが、身寄りのない人や親族に頼れない場合には市区町村長が申立てをするケースもあります。
2023年のデータでは市区町村長による成年後見人等の選任申立て件数が9,607件となり、過去最多を更新しています。
高齢単独世帯の増加に伴い、この件数はさらに増えていくかもしれません。
判断能力が低下してしまった本人に代わり、財産管理や契約などを行える成年後見制度は、悪質商法といった犯罪被害防止の観点からも有効と言えます。
ただし本人の意思を反映するためには任意後見制度の利用も含め、なるべく判断能力が正常なうち検討を進めたい所です。
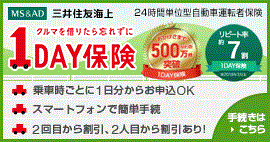 三井住友海上【公式】1日自動車保険はこちら↑
三井住友海上【公式】1日自動車保険はこちら↑
アドバンスリンクLINE公式アカウント
下記ボタンからアドバンスLINE公式アカウントと友だちになります


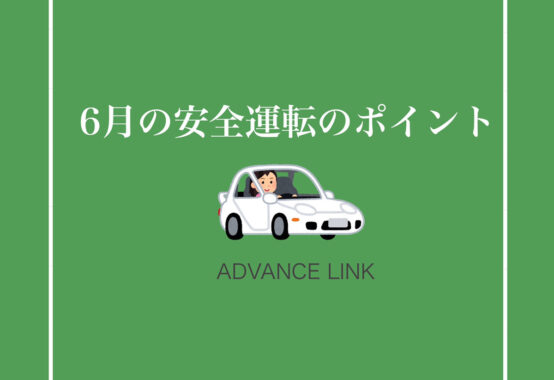

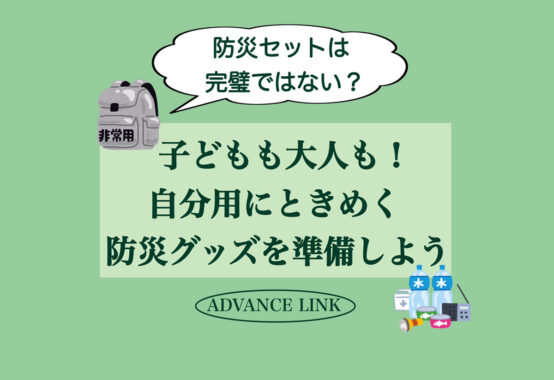

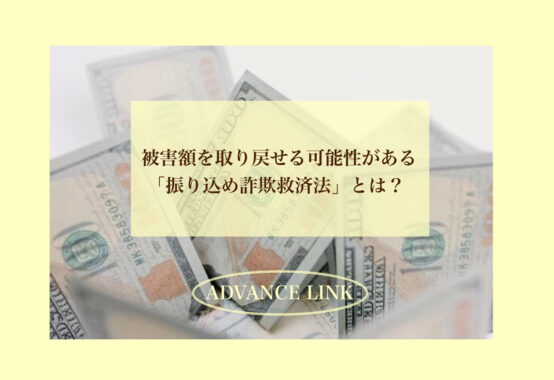



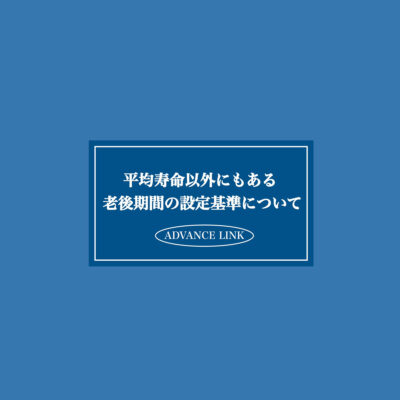
この記事へのコメントはありません。