勤めていた企業等から退職金を受け取った際の税金について、退職所得には一部の例外を除いて2分の1だけ課税されるルールがあります。令和4年分からは税制改正によってその例外の範囲が広がりますが、どのような人が対象となるのでしょうか?
- 短期退職手当等の取り扱い
令和3年分までの段階で退職所得の全額に課税されるのは、役員勤続年数が5年以下で、その役員勤続年数に対応する退職金(特定役員退職手当等)を受け取る場合です。それに加えて令和4年分以後は、役員以外として勤務した期間が5年以下の人について、退職金(短期退職手当等)の額から退職所得控除額を差し引いたうち300万円を超える部分が全額課税となります。
短期退職手当等の取り扱いが適用されるのは、退職金支給の基因となった退職の日が、令和4年1月1日以降の場合です。つまり令和3年12月31日以前に退職した人に支払われた退職金なら、支払日が後日となっても、原則として改正前の規定(2分の1課税の対象)が適用されます。
なお改正後の短期勤続年数の判定について、役員等勤続期間がある場合、それを含んだ年数で行われます。例えば入社から退職までの期間が6年、そのうち最後の2年を役員として勤務した人は、6年を基準に判定(=5年超)されます。したがって使用人(役員以外の者)として勤務した最初の4年間に対応する退職金は短期退職手当等に該当せず、2分の1課税が適用されます。ただし役員として勤務した2年間に対応する退職金は特定役員退職手当等にあたり、全額課税となるため注意が必要です。
- 使用人と役員の期間が混在した短期退職は税額計算が煩雑に
次に短期退職手当等と特定役員退職手当等の、両方が当てはまるケースを考えてみましょう。例えば入社から退職までの期間が5年、そのうち最後の3年を役員として勤務した人は、短期勤続年数5年を基準に判定(=5年以下)されます。したがって役員として勤務した3年間に対応する退職金は特定役員退職手当等に該当し、それ以外の部分に対応する退職金は短期退職手当等に該当します。
このケースで特定役員退職手当等が1,000万円、短期退職手当等が500万円支給された場合、退職所得控除額は勤続1年あたり40万円です。そのため役員として勤務した期間に適用される退職所得控除額は40万円×3年=120万円、使用人として勤務した期間に適用される退職所得控除額は40万円×5年-120万円=80万円となります。
上記をもとに特定役員退職手当等の退職所得金額から考えると、収入金額1,000万円-120万円=880万円と計算されます(その全額が課税対象)。一方で短期退職手当等の退職所得金額は、まず収入金額500万円-80万円=420万円という計算過程から、300万円以下の部分と300万円超の部分に分けて求めなくてはなりません。300万円以下の部分は2分の1課税のため300万円×1/2=150万円、300万円を超える部分(420万円-300万円)は全額課税のため120万円、これらを合算した短期退職手当等に係る退職所得金額は、150万円+120万円=270万円となります。
したがって特定役員退職手当等と短期退職手当等の、退職所得金額の合計は880万円+270万円=1,150万円となり、これに所定の税率を掛けて税額が算出される流れです。以上のように勤続年数が短く使用人と役員の期間が混在したケースでは、退職金にかかる税額の計算が煩雑になります。企業が幹部候補の人材を中途採用するような場合、短期退職のデメリットの一つとして留意した方が良いかもしれません。
【参考】国税庁:短期退職手当等Q&A(令和3年10月)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0021009-037_01.pdf


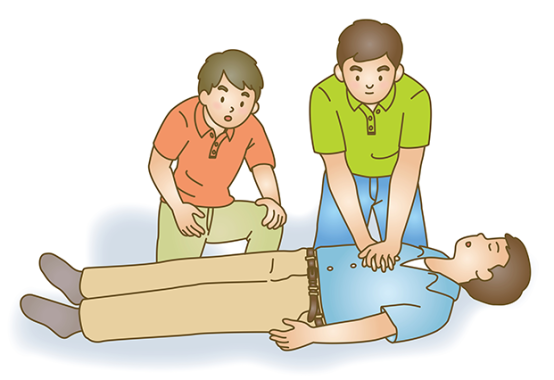
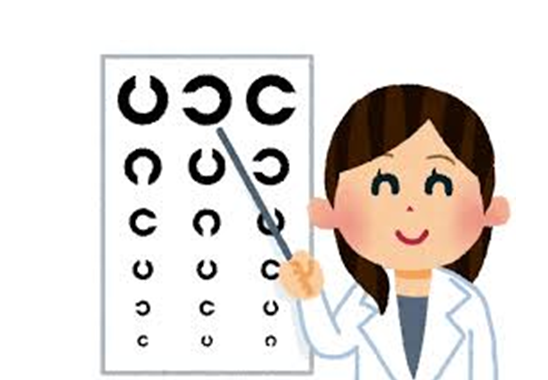





-400x400.png)

この記事へのコメントはありません。