日本人の生涯がん罹患率は高い水準にあり、2人に1人はがんに罹患すると言われています。その治療法も日々進歩していますが、「がんになったら仕事を辞めることになる」と考える人は今も少なくありません。今回は国のがん対策基本法を軸とした、事業主に求められる施策等を紹介します。
| 2016年改正法で基本理念の項目が追加 |
国のがん対策の根幹をなす重要な法律として、2006年にがん対策基本法が成立しました。その目的は国民の生命および健康にとって大きな課題である、がん対策の基本理念や基本事項を定めることによる総合的・計画的な対策推進です。
この法律は2016年に改正が行われ、基本理念に以下のような項目が追加されています。
・がん患者が尊厳を保持しつつ、安心して暮らすことのできる社会の構築
・それぞれのがん特性への配慮
・保健、福祉、雇用、教育その他の関連施策との有機的な連携
・国、地方公共団体、医療保険者、医師、事業主、学校など関係者による密接な相互連携
・がん患者の個人情報保護についての適正な配慮
| 事業主の責務に沿った施策の実行が大切 |
改正がん対策基本法では上記の基本理念追加のほか、「目的規定の改正」「医療保険者および国民の責務の改正」「事業主の責務の新設」「基本計画等の見直し期間の改正」「基本的施策の拡充」といった措置が行われています。
これらのうち特に画期的と思われるのが「事業主の責務の新設」で、努力義務ではあるものの患者の雇用継続、国や地方公共団体が講じるがん対策への協力などについて記載されています。事業主には具体的にどのようなことが求められているのでしょうか?
まず雇用継続について、患者本人の体調と治療計画に合わせ、柔軟な雇用管理を行うことが重要です。時短勤務や時間休を組み込めば、働く意欲も能力もある人が退職せざるを得ない状況の防止につながるでしょう。もちろんこうした勤務形態に対する、職場の理解も大切な要素です。
また、がんへの罹患予防・早期発見を目的とした、がん検診等の実施も施策のメインとして挙げられます。通常の健康診断では見つけにくい病状を発見し、ステージが進行する前に適切な治療を始めることで、本人および事業所の将来的な損失が防げると考えられます。
がんに関する知識の普及も、長期的な視点で欠かしてはならない施策です。学校やメディアで基本知識を一旦吸収したにもかかわらず、「医師から治療方針の説明を受けても理解できない」「身体に異変を感じても行動に移せない」といったケースは珍しくありません。従業員を対象とした定期的なセミナーを開催するなど、単発で終わらない啓発活動を続けていく形が理想といえます。
事業主に対しては従業員が会社の宝であるという認識のもと、それぞれの状況に寄り添える体制を整えることが、強く求められます。
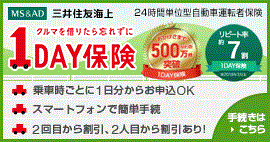 三井住友海上【公式】1日自動車保険はこちら↑
三井住友海上【公式】1日自動車保険はこちら↑
アドバンスリンクLINE公式アカウント
下記ボタンからアドバンスLINE公式アカウントと友だちになります
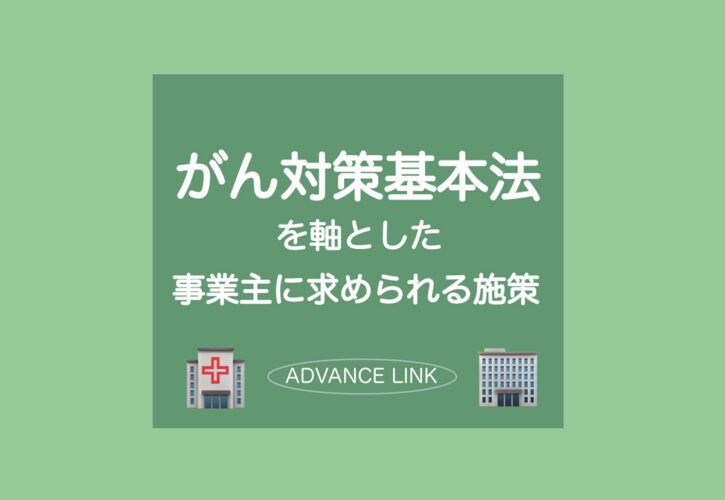

-554x380.png)
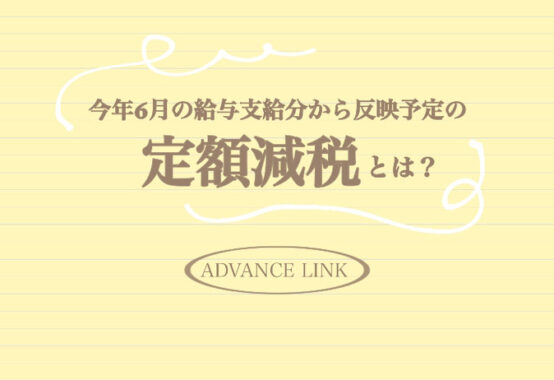
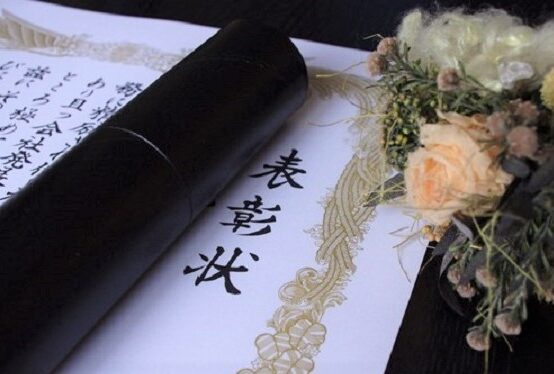





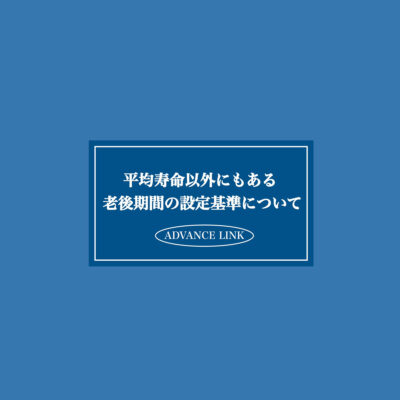
この記事へのコメントはありません。