年代問わずスマホやPCが浸透している現在、故人が使用していた機器の中に入っている各種情報へ、遺族でもアクセスできない問題が頻発しています。後の相続手続きなどで困ることがないよう、デジタル遺品についてポイントを整理しましょう。
| 画面ロックやID・パスワードが家族の重荷に? |
スマホでインターネットを利用する人は60代が約8割、70代が約5割となっています。今や高齢世代でもネット銀行で資産を保有したり、定額制のサービス(サブスク)に加入したりしているケースが多く見られます。
日常的に利用するサービスならスマホやPCにID・パスワードを記憶させ、自動でログインすることも可能ですが、機器本体を起動する際は画面ロックを解除しなくてはならないのが一般的です。
画面ロックは4~6桁の数字パスワード入力など、シンプルな操作で解除される一方、パスワードを知らない他人が容易に解除できない形になっています。プライバシー等の観点から、家族にも解除方法を教えていない方もいるでしょう。
持ち主が健在なうちはそれでも大きな問題はありませんが、機器内の各種ID・パスワードを家族と共有しないまま亡くなってしまった場合、デジタル遺品の問題が浮上します。
| 早めに進めておきたい「デジタル終活」 |
デジタル遺品に明確な定義はありませんが、故人が利用していたインターネット上のIDやパスワード、SNSアカウント、ネット銀行の口座やサブスク契約など、有料・無料を問わず利用可能な状態で残されているデータを指すことが一般的です。
これらの情報が故人と遺族の間で共有されていないと、ネット銀行の相続手続きや、サブスク契約の請求停止などに支障が生じます。機器本体の画面ロックも通信事業者等では解除できず、そこから先に進めない事態となりかねません。こうしたトラブルを防ぐための備えとして、以下のような「デジタル終活」が考えられます。
・画面ロックや各種IDの情報を整理し、遺族が閲覧できる状態にしておく
・パスワードや契約サービスの整理にエンディングノートを活用する
・スマホ等の事業者で遺族のアクセス権限を事前に設定できるサービスを活用する
大切な情報を1つのデジタル機器に集約できるのは便利な一方、いざという時その情報に誰もアクセスできないリスクがあります。デジタル遺品の問題はなるべく先延ばしにせず、各種ID・パスワード情報を書き残すといった対策を早めに進めていくことが望まれます。
【参照】国民生活センター「今から考えておきたいデジタル終活 -スマホの中の見えない契約で遺された家族が困らないために-」
https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20241120_1.html
 三井住友海上 賃貸居住者向け火災保険はこちら↑
三井住友海上 賃貸居住者向け火災保険はこちら↑
アドバンスリンクLINE公式アカウント
下記ボタンからアドバンスLINE公式アカウントと友だちになります
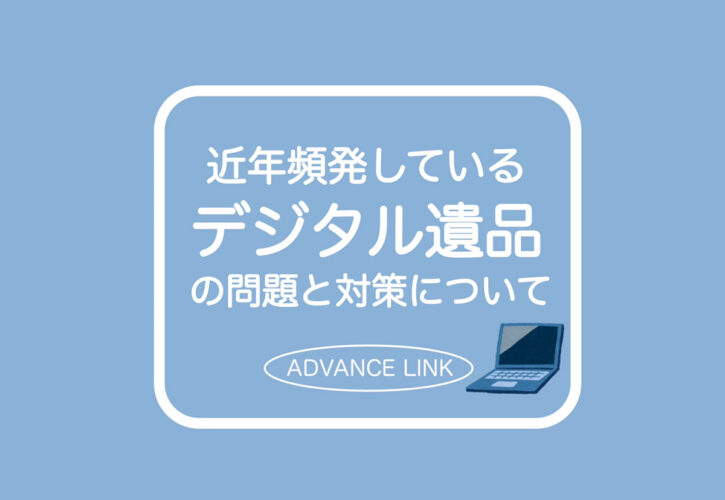


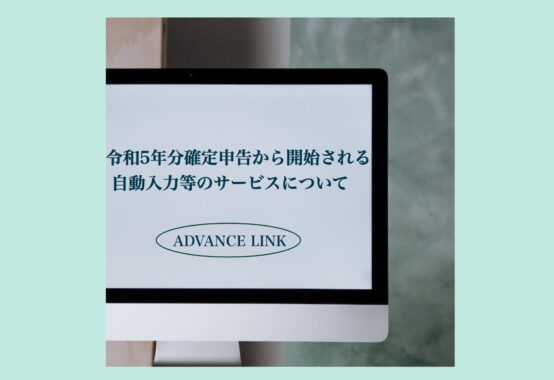

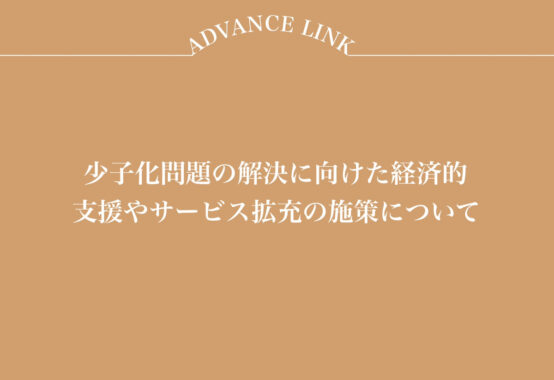


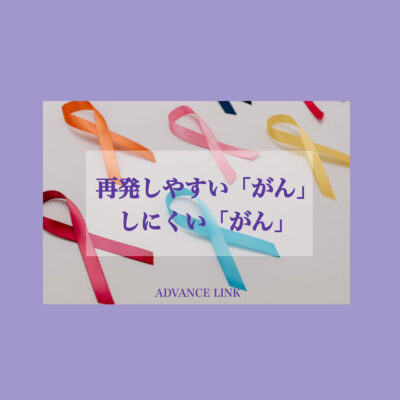


この記事へのコメントはありません。